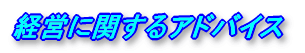
寺 田 税 理 士 事 務 所
![]()
![]() 民事再生法の主な目的は中小企業の再建と倒産防止
民事再生法の主な目的は中小企業の再建と倒産防止
民事再生法は、企業倒産手続きの迅速化を目指し、倒産に伴う資産の劣化や従業員の離散をくい止め、
企業の早期の再建を促進することを主目的としています。
つまり従来の和議手続きの欠点を補い、経営不振の企業の再建や倒産防止を目的に整備されたものです
これまで(民事再生法施行前)の倒産の法的処理は、次のとおりでした。
● 清算型 : 「破産」「特別清算」
● 再建型 : 「和議」「会社更生」「会社整理」
民事再生手続きは、この「和議」手続きに代わるもので、「会社更生」よりも手続きが簡素化されており、
経営者は引き続き企業を経営できます。
なお、民事再生法は今年(平成12年)4月1日より施行されましたが(それに伴って和議法を廃止)、
施行後2ヶ月間で申請数が100件を突破したようです。
![]() 民事再生法の主なポイント
民事再生法の主なポイント
(1)利用対象はすべての法人・個人
すべての法人・個人が利用対象となっています。
従って、有限会社や医療法人、学校法人も利用できます。
(2)早期の申立てが可能
民事再生手続きの申し立てができるのは、債務所及び債権者です。
そしてその申し立ての原因として、次の事項が規定されています。
① 債務者に破産原因の事実が発生する恐れがある。
② 債務者が事業の継続に著しい支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することが
できない
したがって、例えば債務超過や支払不能といった実質的破綻状態になる以前の、破綻が
生じるおそれがあると判断した段階で民事再生手続きの申立てができるのです。
(3)手続き開始前に債務者財産の保全処分
民事再生手続きの申立から手続き開始決定がなされるまでの間、債務者の財産を保全するため
裁判所は「保全処分」が出せるようになりました。
この保全処分には、すべての債権者に対し、債務者財産への強制執行などの禁止を命ずる
「包括的禁止命令」や、担保権者に対する競売手続きの中止命令などがあります。
(4)担保権消滅請求制度
これは、事業継続に不可欠な工場等が担保になっている場合、その財産の価格を金銭で
裁判所に納めれば、担保権を抹消する事が出来るというものです。
(5)再生計画案の可決要件の緩和
再生計画案については、債権者集会の出席債権者の2分の1以上で、かつ、総債券額の
2分の1以上(和議手続きでは4分の3以上)の賛成で可決できるようになり、緩和されています。
(6)再生計画の履行の確保
和議手続きでは再建計画の履行は、債務者任せでしたが、民事再生法では、監督委員のより
計画の履行を監督する事もでき、債務者が再生計画の履行を怠った場合、債権者は再生計画
の取り消しを求めるといったことができます。
<民事再生法と和議法の主な相違点比較>
| 民事再生法 | 和議法 | |
| 申立の時期及び条件 | 早期・緩やか | 激しい |
| 強制執行等の包括的 禁止命令 |
あり | なし |
| 担保権実行の一定の制限 | あり(中止命令) | なし |
| 担保権の抹消許可 | 可能 | なし |
| 再生計画案の可決要件 | 2分の1以上 | 4分の3以上 |
| 再生計画の履行の確保 | 強い | なし |
![]() 民事再生手続きの流れ
民事再生手続きの流れ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() 民事再生法を利用する際の留意事項
民事再生法を利用する際の留意事項
以上のことから、民事再生法は経営不振に陥った企業にとってその再建に効果が期待できそうですが、
利用する際には次のような事項に留意し、慎重に検討する必要があります。
【留意事項】
① 得意先や取引先等の信頼関係が十分築かれている
② 経営者に求心力があり全社一丸となっている
③ 民事再生手続きを申し立てた場合、「倒産企業」と評価される
*ある民間信用調査期間は、民事再生手続きを申し立てた企業を「倒産企業」として扱うようです。
世間では、事実上の倒産と評価されます。
④ 申立後の資金繰りが厳しくなる
⑤ 債務が増加するおそれがある など
*現金での支払いが予想され、未払い金(債務)が膨らむおそれがあります。
![]() 得意先が申し立てたら?
得意先が申し立てたら?
得意先が民事再生手続きを申し立てた場合、例えば、「売掛金が回収できない」「担保権の実行に
一定の制限が加えられる」などのおおきな影響が考えられます。
【対応(一例)】
① 取引を現金との引き換えに代える
② 手形による取引の場合は優良企業が振り出した「回し手形」で受け取る
③ 得意先のキャッシュフローや資金繰りに注意する
④ 再生計画の実施状況を注視する など
事業内容
基本理念
税務相談
人生の応援歌
経営分析
事業概要
E-mail
リンク集
![]()
![]()